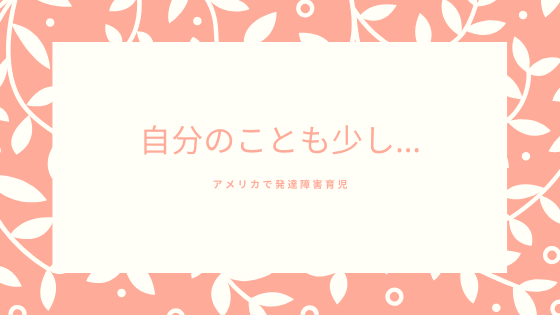実は、6月にDevelopmental Pediatrician に会っていて、無料のNeuropsychiatric Evaluationが受けられなかったことや、息子が学校で泣くことが頻繁にあることを話した結果、次のようなアドバイスを受けていました。
- 学校の School Psychologist に相談し、同じチームとして協力してもらうこと
- 他の機関でも無料でEvaluationを受けられるリストに連絡すること
- 最悪お金を払ってEvaluationを受けること
- Social Skills Groupのサマーキャンプに登録してみること
息子が学校で泣くことが増えた頃、もしかしたらお友達と上手に遊ぶ方法がわからないからなんじゃないか、と思っていたのです。(実際、泣いてた理由は別だったのですが…)オンラインでリサーチしていた結果、どうやらSocial Skills Groupというもので、Social Skills Training (SST)というものを受けることができるらしいということを学びました。
ソーシャルスキルトレーニングとは?
実際にソーシャルスキルを学ぶための「ソーシャルスキルトレーニング」とは、どのようなものなのでしょうか?
ソーシャルスキルトレーニングでは、対人関係や集団生活を営みやすくするための技能(スキル)を養います。
特に発達障害のお子さまにおいては、自身の置かれた状況を読み取ることや、何らかの理由で適切な行動を獲得しづらいことがあり、対人関係上の経験を積み重ねる中で自身で振る舞いを修正・調整していくことが難しいことがあります。
ソーシャルスキルトレーニングでは、お子さまの特性や情緒面、本人を取り巻く環境などにも配慮しながら、社会的スキルのつまづきを補い、集団の中でその子らしく過ごせるように支援します
LITALICOジュニアウェブサイトより
ということで、Facebookで宣伝を見かけた夏の間のSocial Skills Groupにサインアップしてみました!
かかった費用は合計$600.含まれる内容は、自宅での面談と50分x6回のグループセッションです。
セッションは子供たちだけで参加しているので詳しい様子を聞くことはできませんでしたが、異なる感情の勉強、ネガティブな感情(悲しい、同様、怒りなど)を持った時の対処方法、友達を作る(選ぶ)ときに大切なこと、など、ゲームを通して学んでいたようです。
グループのサイズは5人ですし、Licensed Clinical Social Worker (LCSW)主導ということで、息子もすぐに溶け込んですぐに楽しむことができたようです。
今日最後のセッションでしたが、きちんとSelf Advocate(自分のために立ち上がって声をあげること)が 出来ていたということで表彰されていて、本当に誇りに思っています。この部分、私自身の大きな課題で、常日頃もがき苦しんでいるところなので、7歳なのにそんな力があるなんて大尊敬です!